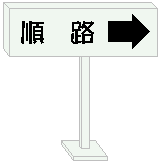| 笹 山 笠 | ||
|
笹山笠は黒崎祇園の原型とも云われ、明治39年以前までは山笠はすべてこの笹山笠だけであった。 現在は お汐いとりの当日に立てられ継承されているが地区により若干飾り方に違いがある。山笠台の中央部に笹を2本 立て注縄でつなぎ、ご神体の意味で須賀神社のお札の前に鏡を取り付け、その周りを杉葉で勾欄にする。勾欄は 神社の欄干を意味し、神域を象徴する勾欄の四隅には布で作った梵天をぶらさげる。 梵天は神の座を示すもの、 欲界の上にあるもののよし、つまり勾欄から上は神の座という事である。山笠台の周囲は幕をで飾り両脇に大きな 提灯を付け、時には連隊旗を飾ったり、花木をつけた例もある。 当時、笹山に用いられる幕は各区費用をかけこ ったもので船町は 「船町」 の図を四囲に刺繍し 「船」 の字を配したものであり同様に田町は田の字を図案化し 藤田は藤の字を形どった。 一方熊手は熊の字に弓を配したものを刺繍していた。 台上の飾りも各区異なり、船町 は船扇を四面に各面四個宛並べ藤田、田町は楯を並べそれに各自区のマークを入れており、熊手は横に国旗を はり弓を配していた。 現在でも多少変化はしたものの、かき棒をかずらで縛り、笹を立てただけのシンプルな山笠 は、その伝統を今に受け継いでいる。 この笹山笠は昭和43年県無形文化財、51年に県無形民俗文化財に指定 された。 |
||
 |
 |
|
かずらを叩いて締めやすくする | かき棒と台にかつらをまわす |
|
 |
 |
|
かつらを締め木を打ち込み固定する | 締めあがった様子 |
|
 |
 |
|
注連縄は長老の仕事である | 杉勾欄を取り付ける |
|
 |
 |
|
竹をあぶり曲げていくこれが太鼓の台となる | 竹に荒縄を巻いていくこれを文字固めと呼ぶ |
|
 |
黒崎祇園 熊西笹山笠 |
|
笹山笠はその飾り付けを終えると降神の儀にて神を迎え入れる。 その後悪疫退散、無病息災、五穀豊穣を祈り 各町内をくまなくまわる。 運行を終えた山笠は昇神の儀にて神を降ろしすぐさま壊される。わずか2、3時間の勇姿である。 寂しい気もするがこれが祭り醍醐味でもある。 解体の終わった山笠は四隅に四本柱をたて飾り山への衣替えを静かに待つ。 |
||
 |
 |
|
笹山運行 | 夜の笹山 |
|
|
|
||